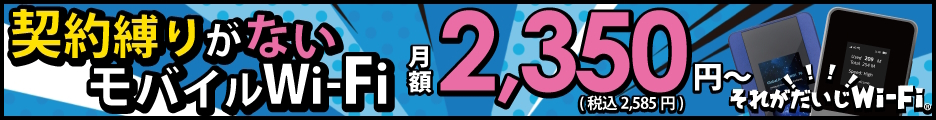法律・法廷に関連した映画1選と、冤罪事件・裁判員制度が題材のミステリー小説4選をご紹介をさせていただきます。
ミステリーを読みながら法律の知識も少しは知りたい、裁判の仕組みももう少し分かればと思っている方に、おすすめしたい作品です。
冤罪・裁判員制度も良くわかる法廷ミステリー小説4選+映画1作品
2009年から開始された裁判員制度。
人が人を裁くそんな法廷の決断に視点を置き、映画1作品小説4選をご紹介させていただきます。
①「それでも僕はやっていない」諏訪正行(監督・脚本)映画
満員電車の中、女子高生に痴漢と摘発されたフリーターの青年が逮捕され、裁判にかけられる話です。
いくらやっていないと主張しても、彼の主張は受け入れてもらえないのです。
検察側は証拠提出を「不見当」としたにも関わらず、裁判所は起訴に踏み切ってしまうのです。
この場合、日本の法律では、ほぼ100%有罪が確定してしまうのです。
ここが見どころ
検察及び裁判所が、いかに容疑者を有罪にしようかとする姿勢に疑問を抱いてしまいます。
人が人を裁くのは本当に難しいことが実感でき、冤罪事件が引き起こす社会的制裁も痛感できる作品です。
②「裁判員法廷」芦辺拓
裁判員裁判制度を対象とした、3部で構成された作品です。
その一「審理」:弁護士と検察官の攻防を中心に事件の真相を明らかにしていく内容です。
その二「評議」:裁判員たちが審議後に討議を行い、主人公の「あなた」の主観が伺える内容です。
その三「自白」:この三部作品の一番のクライマックスシーンが満載されている内容です。
ここがポイント
審理と評議は自白の伏線であったかのように描かれています。
裁判員裁判制度が導入され、今まで裁判所や弁護士、検察官に委ねていた裁判そのものが、われわれ国民がかかわることになった以上、責任は重大であることが感じられる作品です。
③「被告A」折原一
殺人事件で逮捕された男が、冤罪を主張し、また息子を誘拐された母親が犯人に挑んでいくという法廷劇と誘拐劇が同時進行する2つの話が綴られています。
ここがポイント
様々などんでん返しが繰り広げられて、終盤にこの二つの事件が関わりを持ってくるという衝撃の展開になります。
折原氏お得意の叙述トリックではなく、新趣向が伺える作品に仕上がっています。
④「目撃」深谷忠記
主人公である小説家、曽我が8歳の時、母親が父親を刺殺する事件を目撃してしまうのです。
そして39年後、曽我は夫を毒殺して懲役10年の判決を受けた女性からの手紙を受け取り、旧友の弁護士とともに事件に関わり、その女性の無罪を追求していく展開になります。
これら二つの事件は全く接点が無いように思われますが、目撃という共通点によって、大きな展開を見せるのです。
ここがポイント
「目撃」こそがこの作品の真髄を物語っているのです。
まさしく法定心理ミステリーと呼べる作品です。
⑤「最後の証人」柚月裕子
元検事の左方が弁護士として、物的証拠が揃っていて、有罪が濃厚とされている殺人事件の弁護を引き受ける話です。
検察や警察による不正に立ち向かい、毅然とした態度で佐方は挑んでいくのです。
ここがポイント
事件の裏側に隠れた真相を佐方は手繰り寄せていき、それが子供を事故で失った夫婦の復讐劇に発展していくのです。
違った意味の夫婦愛が、感じられる作品です。
まとめ
テレビなどでよく裁判所の光景が写し出されるドラマがあります。
被告がいてその両側に弁護人と検察官そして正面に裁判官。
判決が下される瞬間、被告の人生が変わると言っても過言はないと思います。
人が人を裁く裁判制度、本当に真実の判決が下されているのか。
裁判員制度が始まって10年以上が経過しています。
明日、あなたの手元にも裁判所から手紙が届くかもしれません。