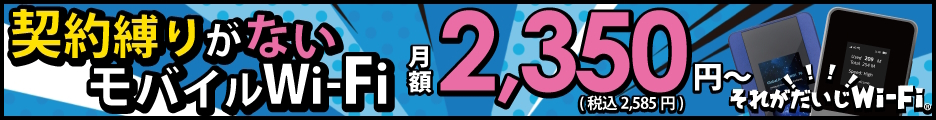戦後の日本文学の旗手として名高い、三島由紀夫氏のおすすめ作品12選をご紹介させていただきます。
東京帝国大学在学中の1944年に、処女創作集の「花ざかりの森」を刊行します。
1947年大学卒業後、大蔵省に勤務するも9ヶ月で退職、1949年に刊行した「仮面の告白」という作品で名声を確立し、以後、文筆活動に専念していきます。
三島由紀夫おすすめ12選をご紹介~鋭い感受性で人間を描く~
世の良識の不道徳、退廃とするものを雅な文体と構成で描写した作品を多く執筆していて、その後の作品も数多くの文学賞を受賞しています。
戦後の日本文学界を代表する作家の一人であると同時に、ノーベル文学賞候補になるなど、海外においても、広く認められた作家であったのです。
晩年、民間防衛組織である「楯の会」を結成し、政治活動に傾倒していき、1970年11月25日に楯の会の会員4名と共に、自衛隊の市ヶ谷駐屯地を訪れ、東部方面総監を監禁します。
そして憲法改正の為のクーデターを促す演説をした後で衝撃的な割腹自殺を図り、45歳の人生に幕を閉じています。
そんな国内の政治活動や文学界に大きな影響を及ぼした、三島由紀夫氏のおすすめの作品12選をご堪能ください。
1、『仮面の告白』
人には言えない性的なものを、自分はおかしいと思いながらも、仮面を被ろうとする主人公の話です。
何人かとの女性との交わりを持っていながら、女性に興味を抱く知人・友人とは違う特異な感情を持ち、同性にも恋い慕ってしまう主人公の苦悩が赤裸々に綴られています。
ここがポイント
同性愛者の主人公の孤独な告白であり、青年期に誰もが陥ってしまう劣等感と自己陶酔をより深淵なものにして、物語全体にねっとりとした薄い影を投じています。
美しく詩的な描写と論理的な文章に、狂気的な程の魅力を感じてしまう作品です。
2、『潮騒』
都会から隔絶された島を舞台に、逞しい若者と美しい少女の若い恋が描かれている話です。
繊細で美しい文章から、隔絶された島の家々や静かなる活気に溢れた人々等、島を包み込む潮風と潮騒が感じとれます。
寡黙ながら情熱のある若者、新治と島に引っ越してきた美しい少女、初江が、まるで引き合わされたようにキスをしたり、嵐の夜に裸で抱き合ったりしても、それ以上の触れ合いの描写がないことで、文体自体に崇高で官能的な美を感じてしまいます。
ここがポイント
三島氏の作家としての息遣いが感じられ、現代の古典に誘う作品として、若い世代にも是非、読んでもらいたいです。
3、『金閣寺』
吃音の悩みを抱えて、その永遠の美に憑りつかれた若き学僧が、金閣寺を燃やすまでを描いた話です。
生まれつきの吃音を持つ主人公は自分の気持ちなど、他人に分かるはずはないと考え、あたかも周囲を切り捨てるように行動し、内面の孤独を極めて行くのです。
ここがポイント
どうして破滅的な思考に向かっていくのか、自らを殊更に貶めることにより、自意識を肥大させて、次第に暗い考えに支配されていく心理状態に引き込まれてしまいます。
負の感情の連鎖により、何故、事件に至ったのかがとても分かり易く、三島文学の最高峰に位置する作品だと思います。
4、『鹿鳴館』
男女間の愛が織りなす、美と悲劇が描かれた4編からなる戯曲集です。
執筆当時、三島氏が文学座に籍を置いていた時の作品であり、どの作品も女性が主役で男性は脇役です。
ここがポイント
明治時代の華族の世界を中年男女の過去の色恋沙汰や、その当時の浮気を虚々実々の駆け引きで、生き生きと描いています。
情緒豊かで言葉遣いの美しい女性たちの遣り取りは、終始おっとりとしていて、気品に溢れています。
人間の感情を上手く描き出した文体であり、強くて醜い嫉妬と、随所に見えるユーモアのバランスが絶妙な作品です。
5、『不道徳教育講座』
世間一般で使われる常套句を反転することにより、キレイごとの裏にある実際を解き明かしていくエッセイです。
どれもこれも、不道徳を推奨するような題目ですが、巧みにひねられていて、いつの間にか道徳的なオチに誘導されてしまうのです。
「友人を裏切るべし」とか「人の不幸を喜ぶべし」など、一見して荒唐無稽なタイトルが並んでいます。
ここがポイント
そうなんです最初から最後まで、三島氏独特のユーモアのある皮肉と明晰なロジックで存分に楽しませてくれます。
純文学作品では感じられない、全く別の三島氏の一面を見ることができる作品です。
6、『鏡子の家』
娘と二人住まいのサロンのような鏡子の家に、緩やかな結束で集まる男女の様々な人生をオムニバス風に描いた話です。
彼らは頽廃的で、偽悪的であり、自らの求めるものに対しては貪欲で、さらに心の内側は屈折していて、こだわりがないようで、誇りを持っている厄介な人間たちなのです。
この話の主人公は、彼女の家に出入りする、エリート社員、拳闘家、画家そして俳優の卵の4人の若者なのです。
各々が自分の中にある虚無を自覚していて、鏡子の家で本来の自分を取り戻していくのです。
ここがポイント
言うまでもなく、彼らは三島氏の分身なのです。
男という生き物の性質をよく捉えている作品です。
7、『午後の曳航』
早熟で賢い少年たちが、大人に対して自分たちなりの、大きな正義の鉄槌を振り下ろす話です。
船乗りの竜二に憧れと理想を描いていた少年の登が、未亡人である自分の母との情事を見ることにより、やがて憎悪を覚えていくのです。
矮小な世間とは無縁であった海の男が、結婚を考え、陸の生活に馴染んでいくことが、登にとっては許し難い屈辱であったのです。
ここがポイント
そして大人に対する歪曲した脆い理念や理想が、まるで熱病のように少年たちを捻じ曲げていってしまったのです。
「金閣寺」に勝るとも劣らない三島文学作品です。
8、『禁色』
老作家の檜俊輔が、女性を愛せない同性愛者の美少年の悠一を操って、かつて自分を拒んだ女性たちに復讐をする話です。
社会的地位と名声を確立している大人たちが、精神性をもたない美貌の青年である悠一に惹かれて、翻弄されていく姿が滑稽で陳腐に表現されています。
女性蔑視ともとられかねない内容ですが、不快ではなく、そう感じさせる格調高い圧倒的な筆力に敬服してしまいます。
ここがポイント
美にまつわる欲を通じて、人間の人間らしさが生き生きと大胆かつ繊細に描かれています。
圧倒的かつ緻密な構成で、精神の意味を問われる作品です。
9、『春の雪 豊饒の海 第一巻』
維新の功臣を祖父に持つ侯爵家の若き嫡子である、松枝清顕と、伯爵家の美貌の令嬢、綾倉聡子のついに結ばれることのない恋の話です。
矜(ほこ)り高い青年が、禁じられた恋に生命を賭して求めたものは、一体何だったのでしょうか。
大正初期、明治という一つの時代が終わり、昭和へと移り変わる過渡期にあって、少年から青年へと上手く脱却できないでいる主人公が、その美貌と虚栄心から破滅的な快楽へと墜ちていく様が、巧みな心理描写で描かれています。
ここがポイント
シリーズを通して描かれるのは「輪廻転生」と三島氏の永遠のテーマであった美なのです。
まさしく圧倒的な存在感のある作品です。
10、『葉隠入門』
「葉隠」は今から300年以上も前に佐賀、鍋島藩に仕えた山本常朝が、武士道における覚悟を説いた修養の書ですが、その「葉隠」を解説しつつ、三島氏自身の思想・哲学を説いたものです。
私たちは普段ほとんど、よほどのことがない限り「死」というものを意識することはありません。
どうすれば健康で楽しい人生が送れるだろうかなど、幸福を手に入れることに心を砕いているのです。
生きること、それ自体が目的になり、生きて何を成し遂げていきたいのかという事を徐々に、忘れていってしまっているかもしれません。
ここがポイント
死ぬべき時に死ねる覚悟があるのか、死を考えることが生をたかめることになるのです。
三島氏をあの行動に駆り立てた、思想の一端に触れることができる作品です。
11、『命売ります』
自殺に失敗した男が、他動的に死ぬために命を売りに出す話です。
自殺未遂した男、山田羽仁男が自分の命を売り出し、命を代償としたいろいろな仕事の依頼を受けますが、毎度、死に損ない、生きながらえてしまうのです。
命を売り出したことで、命を狙われることになりますが、いざ殺されそうな事態に直面すると、自分の命への執着が生まれてきてしまうのです。
世界が意味あるものに変われば、死んでも悔いはないという気持ちと、世界が無意味だから、死んでもかまわないという気持ちとはどこで折り合いがつくのでしょうか。
ここがポイント
生きたいという欲望が、全ての物事を複雑怪奇に見せてしまうのでしょうか。
追い込まれた人間の描写が、三島氏の独特の文体で味わえる作品です。
12、『花ざかりの森・憂国 自選短編集』
三島氏自身の解説が載っている13編からなる自選短編集です。
これぞ三島文学だと言わんばかりの文章の流麗さと、計算され尽くした物語の構成は流石に唸ってしまいます。
ここがポイント
一編一編に刻まれた三島氏の思考の片鱗に、心を揺さぶられる思いでいっぱいになります。
中でもやはり「憂国」は強烈であり、恍惚とした覚悟に彩られた濃厚な情景、三島氏の美学に引き込まれてしまいます。
異様な気合のみなぎりを感じてしまう、強烈な作品です。
まとめ
いかがでしたでしょうか、希代の天才作家、三島由紀夫氏の選りすぐった作品を12選ご紹介させていただきました。
三島氏の作品や思想は、良くも悪くも世代を超えて、多大な影響を与えているのではないでしょうか。
まだ読んでいない作品がありましたら、是非この機会に読んでみてください。
そして、三島氏の大いなる覚悟を感じ取っていただければと思います。